化学調味料について特集されているテレビを見ていたら
「化学調味料というものはない」という衝撃の事実を放送していました。
そういえば、テレビの料理番組でも「化学調味料」と聞いたことがありません。
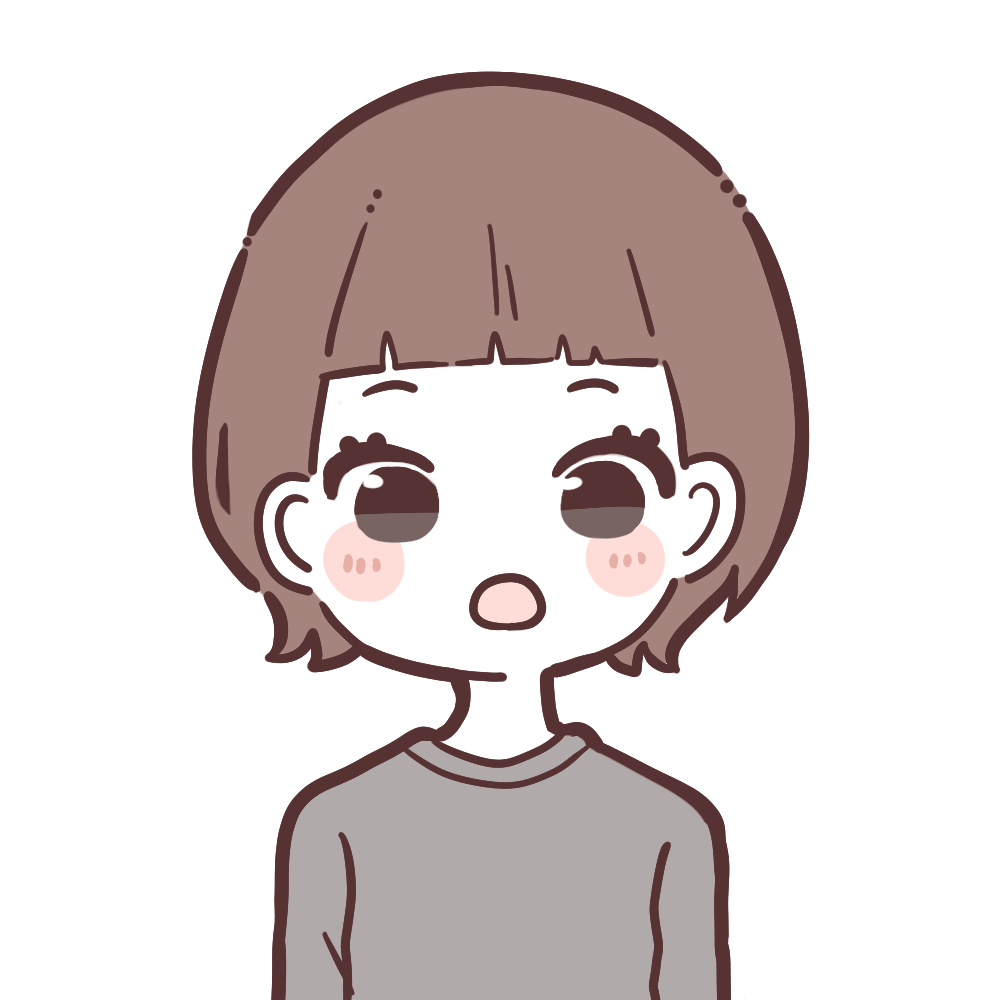 さみい
さみいうま味調味料って言ってるよね
実は「化学調味料」はNHKの料理番組で生まれた言葉で、化学調味料の定義はないことがわかりました!
- 化学調味料の歴史
- 化学調味料はテレビで放送禁止用語なの?
- 化学調味料は危険なの?
今回は「化学調味料」とういう言葉が生まれた理由やテレビで放送禁止用語になっているのは本当なのか?について調べてみました。
化学調味料はいつ生まれた言葉?


明治40年に日本の化学者である池田菊苗氏が昆布のうま味「グルタミン酸」を発見しました。
そして明治41年にグルタミン酸ナトリウムから調味料が作られたと言われています。
日本で最初に販売されたのが「味の素」です。
発売当時は万能調味料や人造調味料などと呼ばれていました。
それが化学調味料と呼ばれるようになったのは、昭和30年にNHKの料理番組で万能調味料が使われたことがきっかけでした。
NHKは公共放送のため、番組内で使用する調味料の商品名を出すことができなかったので
代わりになる言葉として「化学調味料」という言葉が使われることになっていったとのこと。
当時は終戦後10年ほどの時代。
科学が未来を明るくしていくという希望や、憧れなどもあり「科学」という言葉はポジティブに捉えられていました。
そういった時代背景もあり「科学」にかけて「化学調味料」と呼ぶことにしたのではないか?と言われています。
化学調味料がうま味調味料になった?放送禁止用語なの?
化学調味料という言葉が生まれた当時は「科学」はとてもすごい技術。
SFマンガや科学の力で未来が作られているという時代だったので
発展をイメージさせるポジティブな言葉だったそう。
ですが、1970年代ころから公害病などの問題が多く出てくるようになってきて
「科学(化学)」という言葉に国民がネガティブなイメージを持つように。
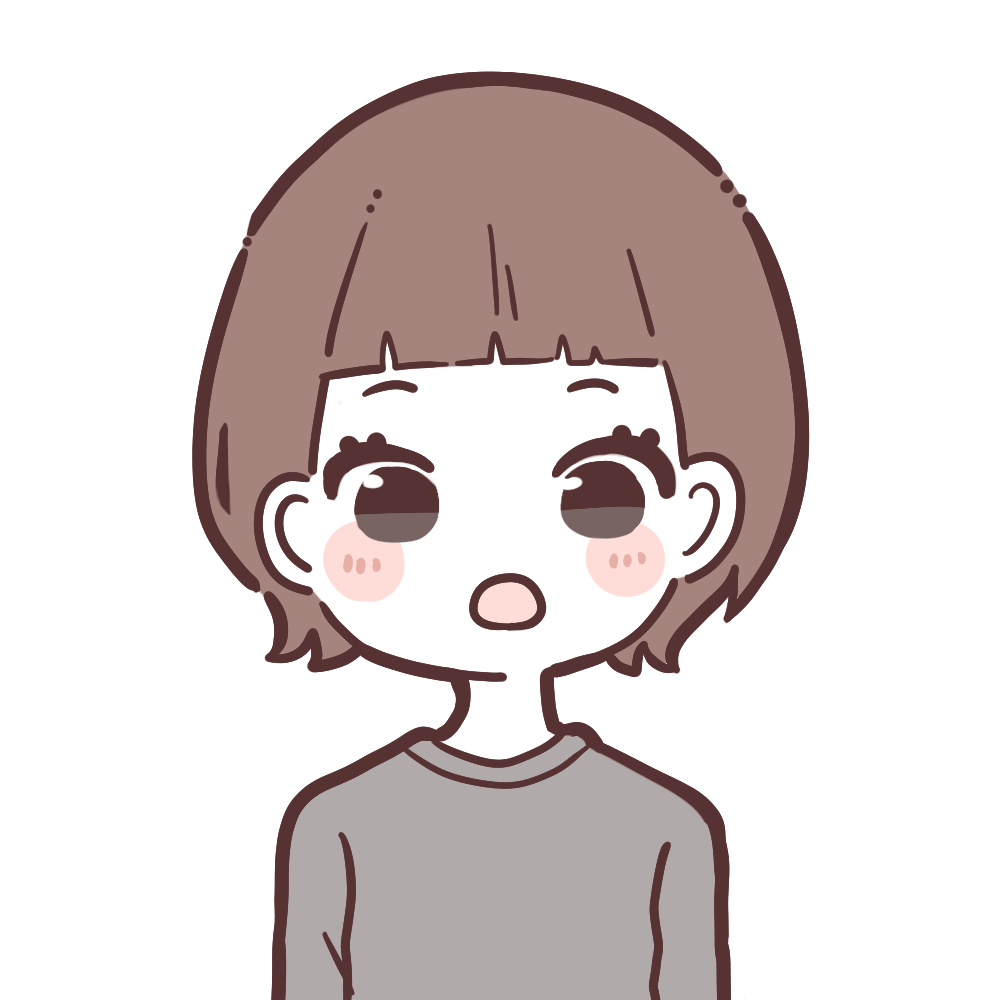
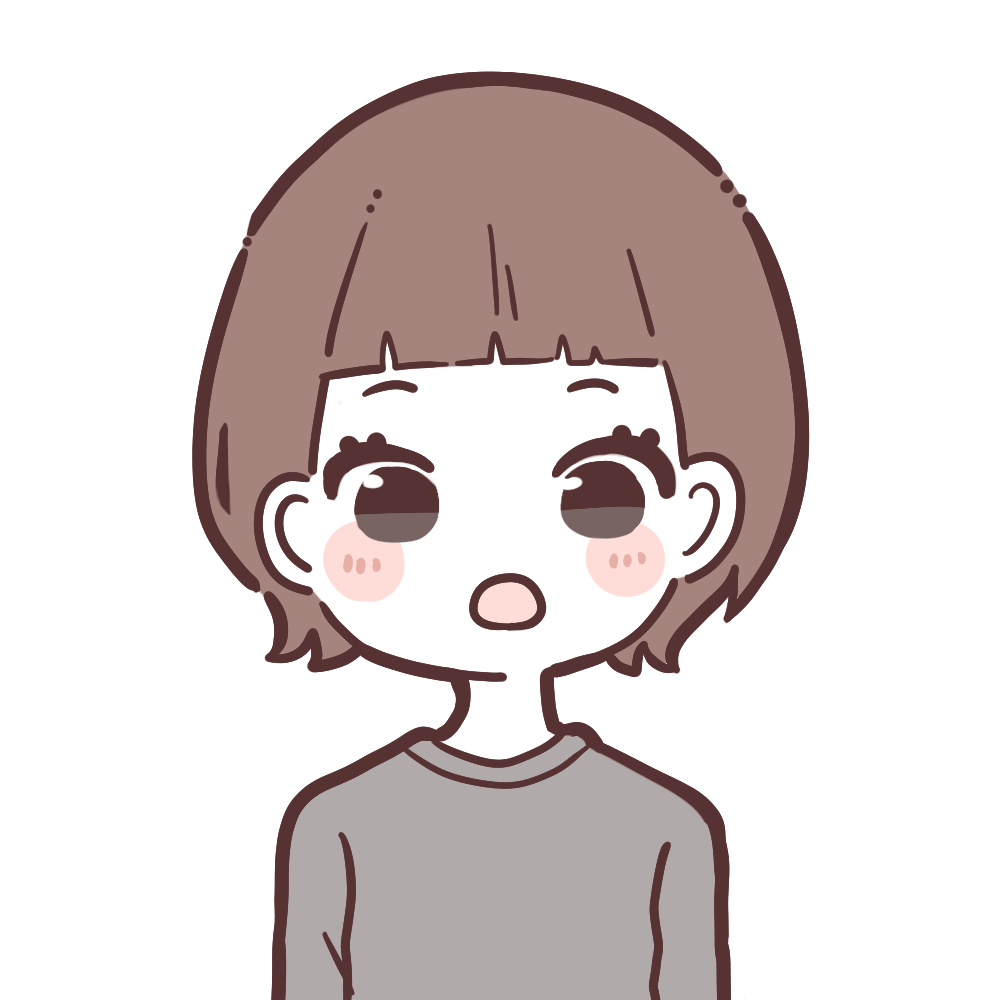
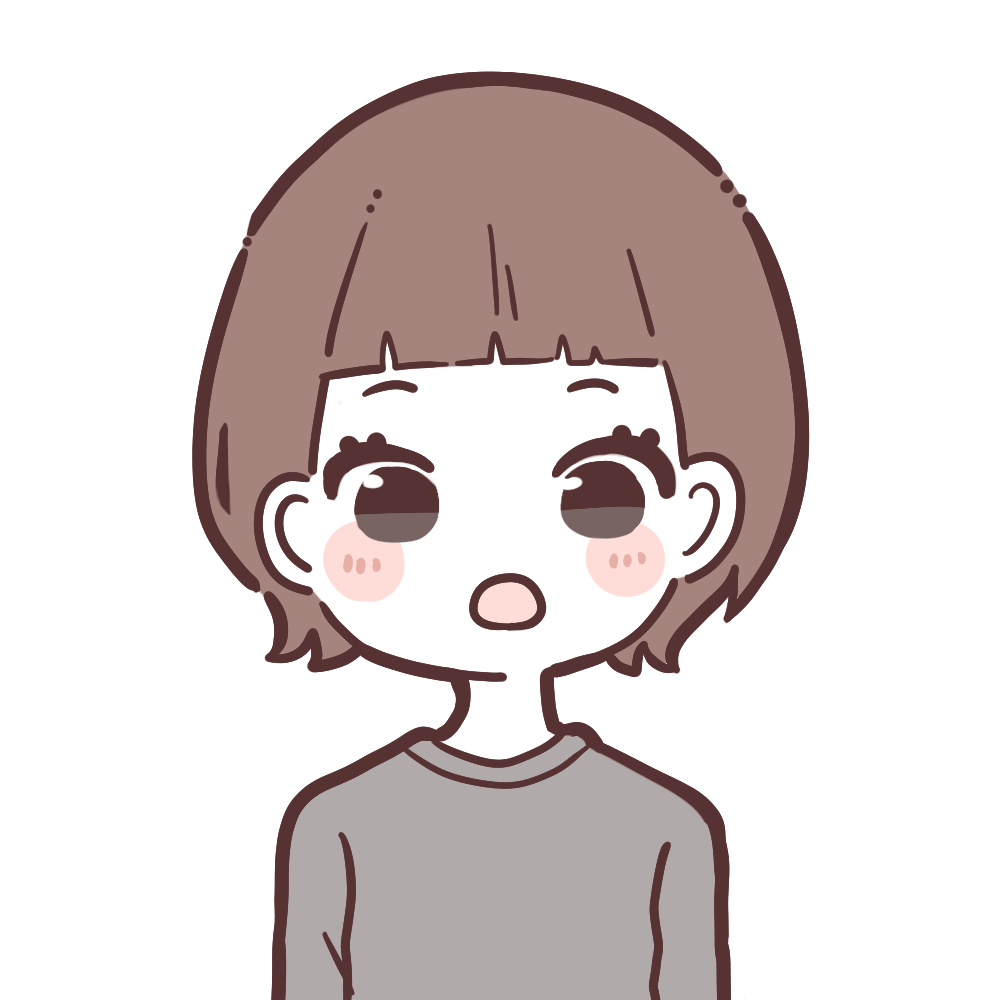
化学と公害が結びついちゃったんだって
そこで、1980年代以降では「うま味調味料」という呼び方に変えて、テレビなどでも「うま味調味料」が使われるようになっていきました。
1990年に改訂された「日本標準商品分類」(現総務省)や2002年に改定された「日本標準産業分類」(総務省)などの行政用語も化学調味料からうま味調味料に変更されています。
うま味調味料協会
行政用語がうま味調味料に変わっているので、テレビでは「化学調味料」という言葉が使われなくなったというこということです。
化学調味料は危険なの?
化学調味料=うま味調味料ということで、なんとなく体に良くないイメージが染み付いていますよね(汗)
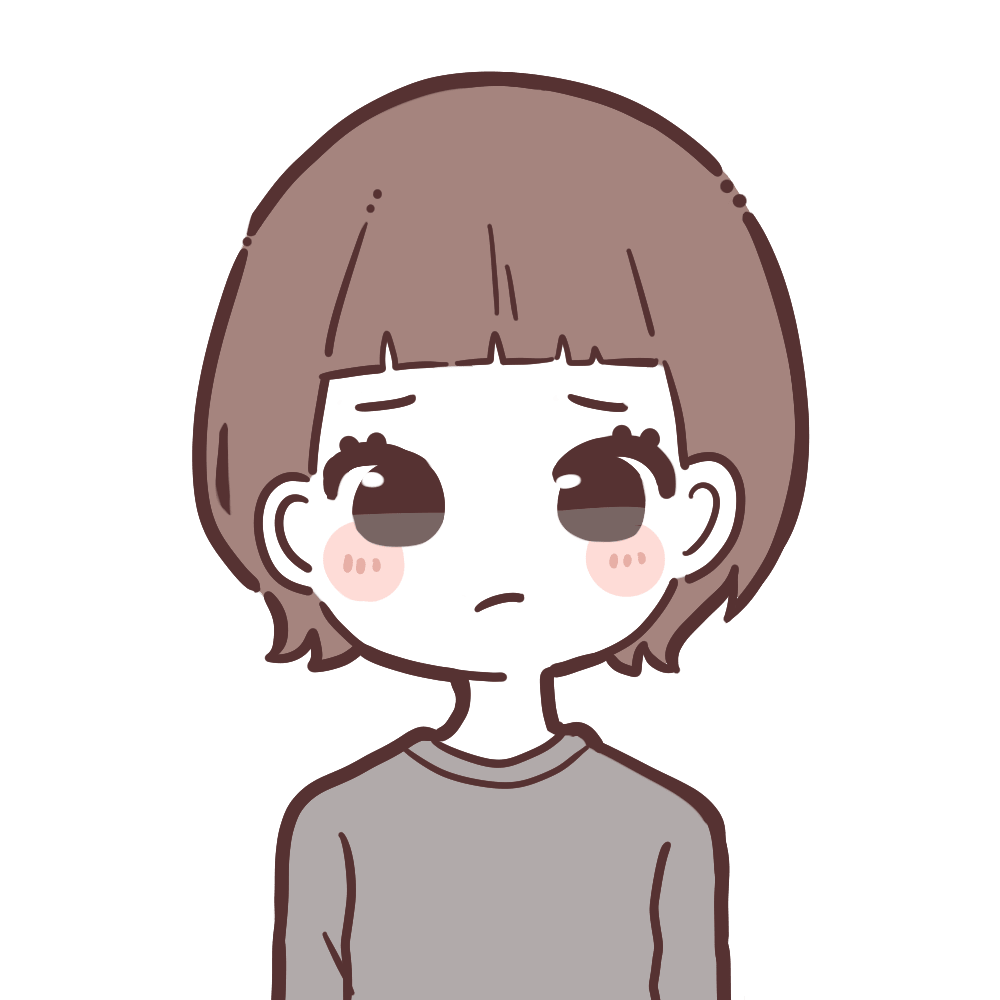
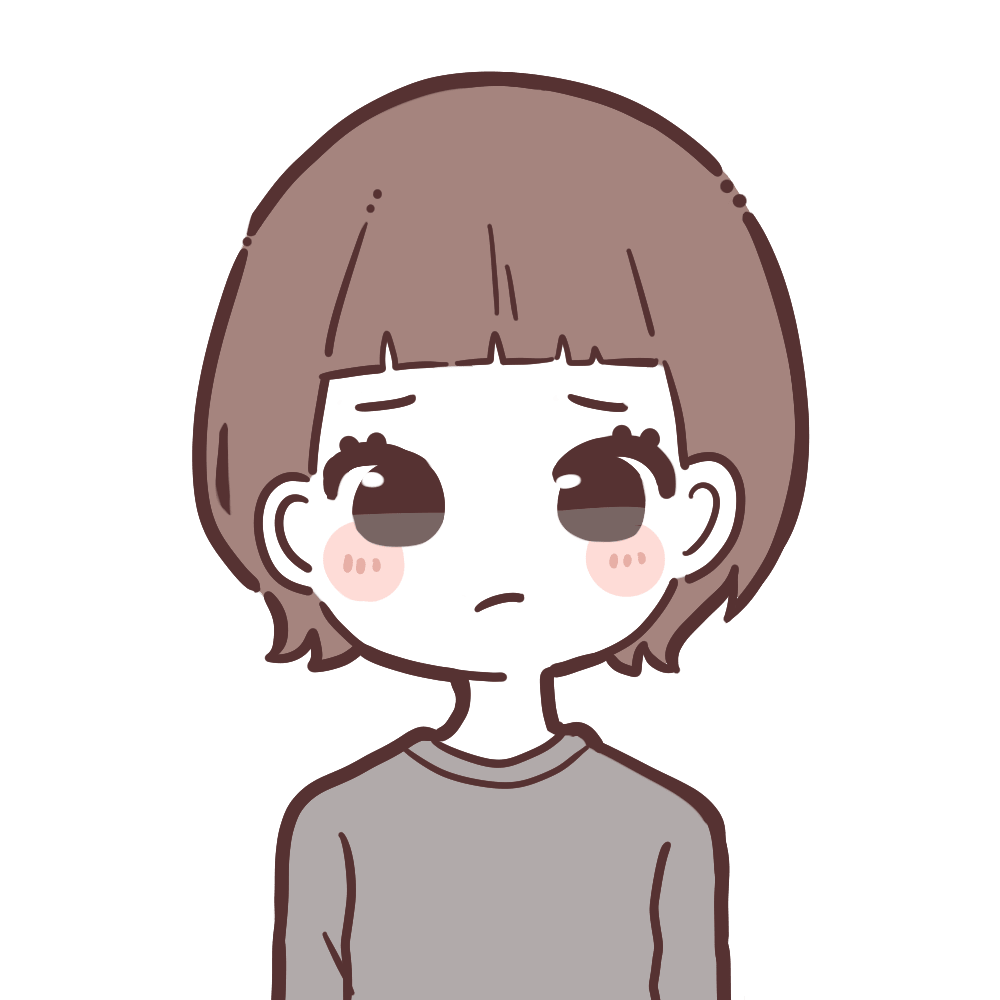
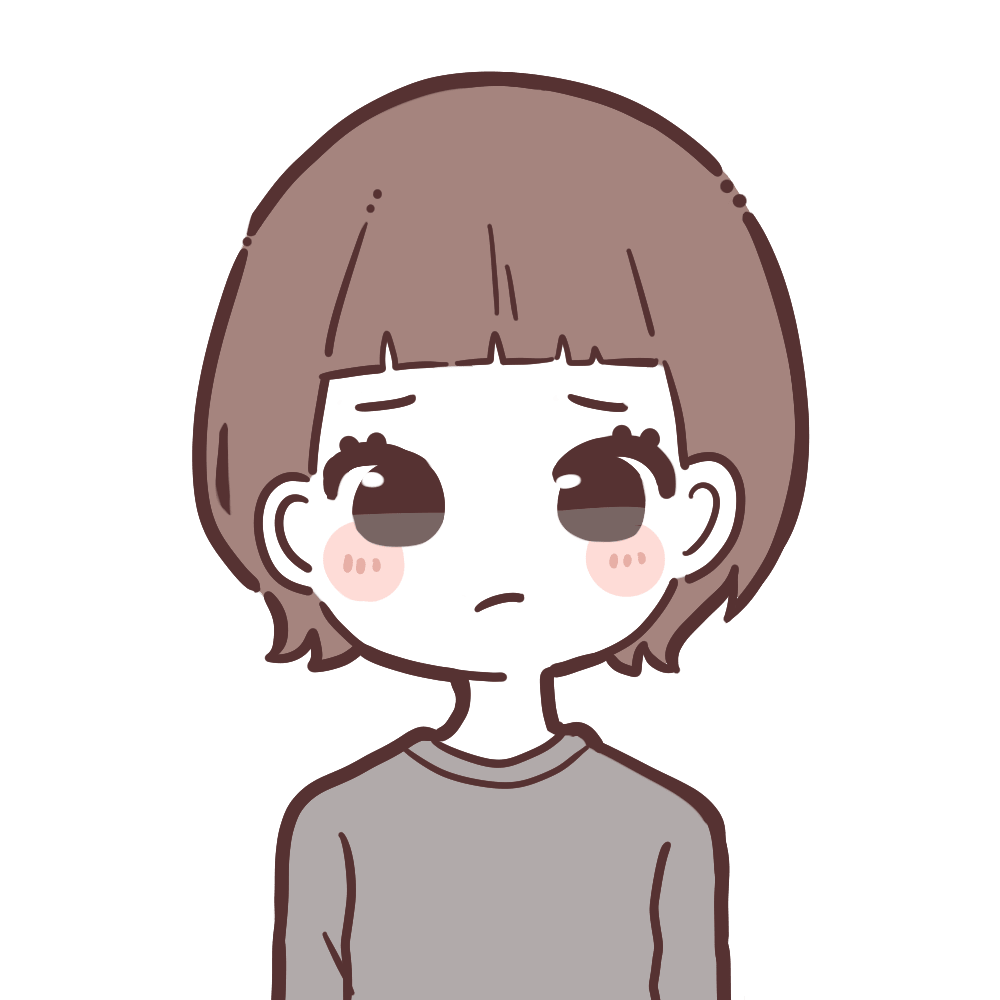
私も母に食べないほうが良いと言われて育ちました
味の素は石油から作られているという話も聞いたことがありますが
実際に1970年代ころまで、味の素は石油由来の原料から作られている時期があったそうです。
味の素社は1950年から様々な原料を使ってグルタミン酸を合成する方法を研究し、最終的にアクリロニトリルと言われる物質からグルタミン酸を作ることに成功しています。
タカギチ事務所
現在の味の素はサトウキビを原料に作られています。
うま味調味料に含まれている旨味成分(グルタミン酸ナトリウム)は昆布だしの中に含まれているもので
- 国連食糧農業機構(FAO)
- 世界保健機構(WHO)
- 合同食品添加物専門家会議(FECFA)
安全な食品添加物として認められています。※日本うま味調味料協会
また、赤ちゃんや妊婦さんが食べても安全であることが確認されているとのことです。
うま味調味料は、母体はもちろん、胎児や乳幼児にとっても問題なく、安全であることが確認されています。生まれてはじめて口にする母乳にももともとグルタミン酸がたくさん含まれています。また、「うま味調味料」の安全性を調べるための実験では、母親の血液中のグルタミン酸濃度を高くしても、胎児の血液中のグルタミン酸濃度は高くならないことが確認されています。
日本うま味調味料協会
味の素の作り方は?
サトウキビからどうやって「うま味調味料」が作られるのか調べてみました。
原料となるサトウキビやキャッサバ芋を絞って糖蜜をつくる
発酵菌の力で糖蜜の中の糖分をグルタミン酸に変化させる
結晶化させたのもが味の素として売られる
他のメーカーのうま味調味料に関してもサトウキビの糖蜜やとうもろこしの澱粉などから作られることが多いそうです。
ウィキペディアの情報によると製造過程で発泡を抑える添加剤が加えられていると掲載されていました。
発酵過程でビオチンを阻害するなど、グルタミン酸生産菌のグルタミン酸生産を活性化する添加剤や、窒素源(硫酸アンモニウム、抗生物質、界面活性剤など)、発泡を調整する薬剤、添加剤が加えられる。
ウィキペディア
食品の裏側2という本でも「驚くべきその製法」という見出しで、うま味調味料の製造方法について紹介されていました。
ある食品メーカーがバクテリアの遺伝子を組み替えることによって、これらの「糖蜜」からグルタミン酸を吐き出す「菌」を作り上げました。
この「菌」が作り出すグルタミン酸を精製して、炭酸ソーダで酸・アルカリの中和反応によって「グルタミン酸Na(ソーダ)」という化学物質に作り上げるのです。
食品の裏側2実態編 232p「調味料(アミノ酸等) 驚くべきその製法」
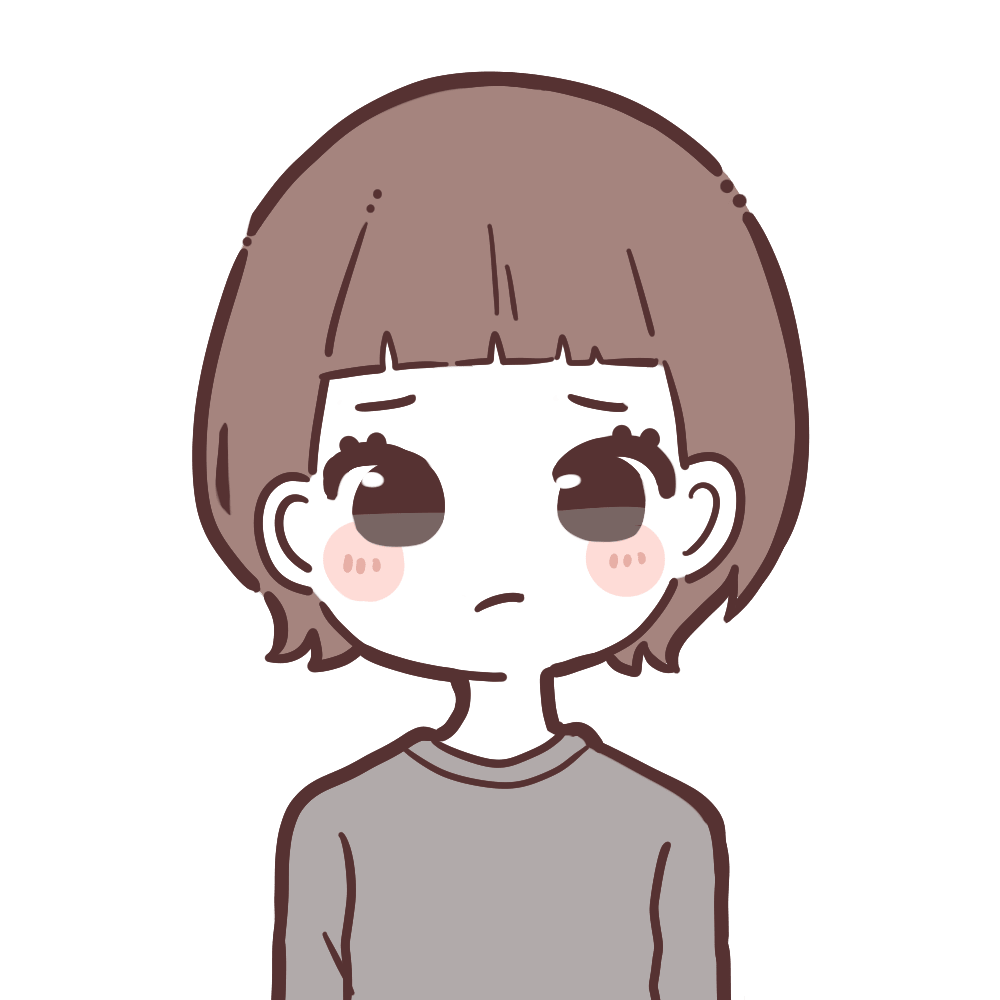
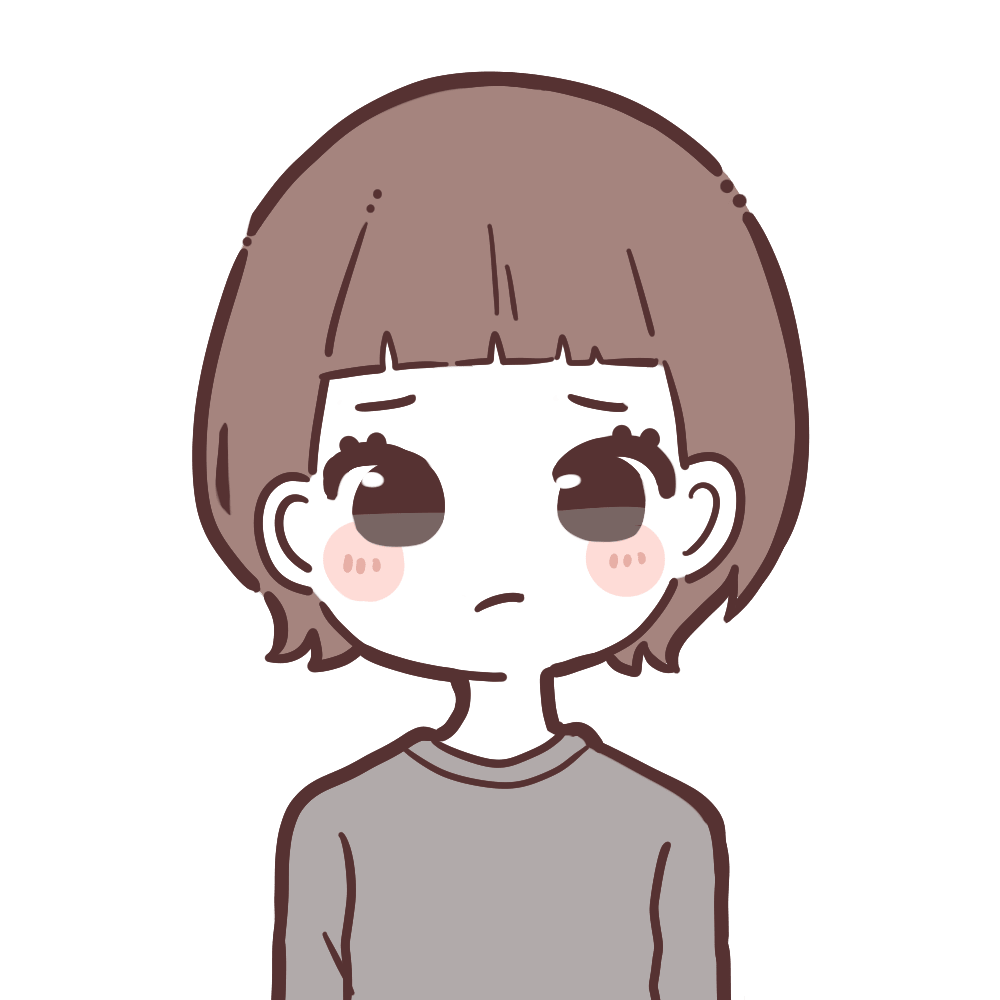
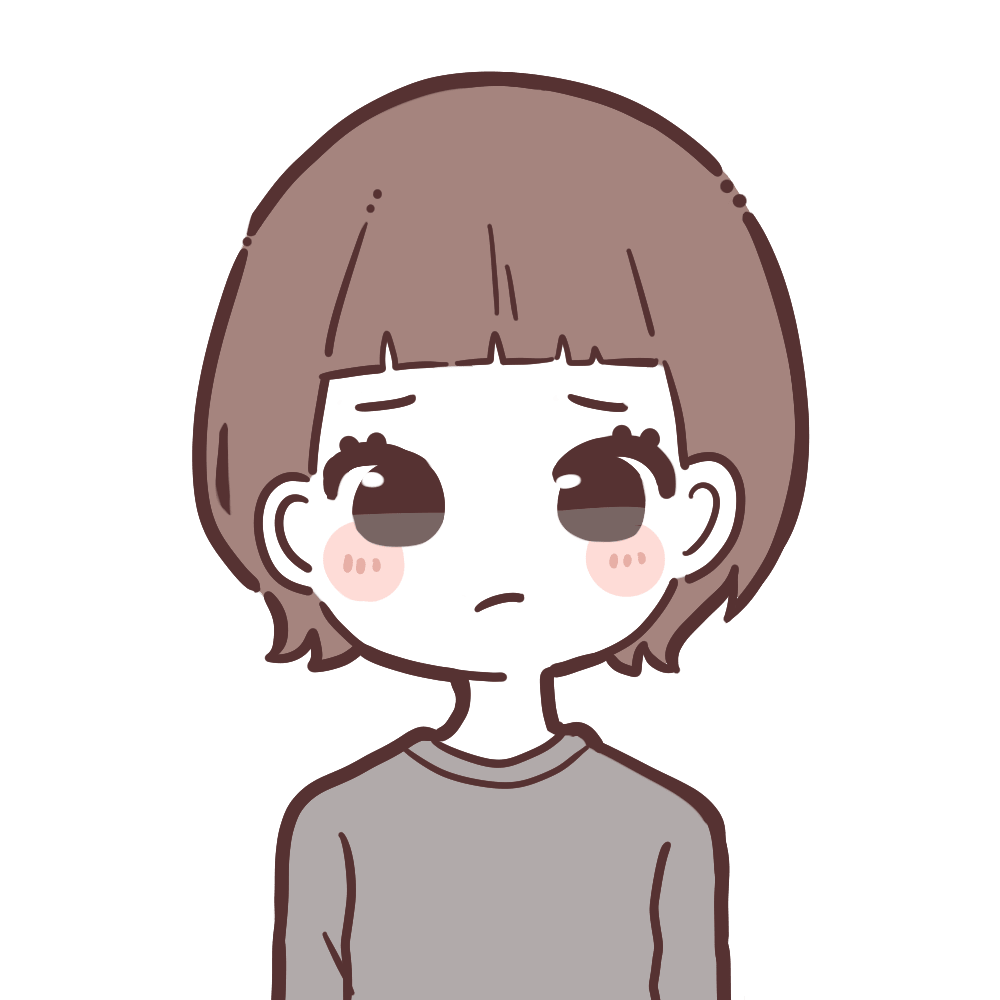
これをみると何が本当で何が嘘なのかよくわからなくなってくるね・・
化学調味料は食品添加物
化学調味料(うま味調味料)は安全な食品添加物として認められていることがわかりました。
コンビニやスーパーなどで売っている商品の原材料では「アミノ酸等」「発酵調味料」という表示で使われていることが多いので、実は身近な食べ物にも使われているうま味調味料です。
メーカー側では安全と確認が取れていると発表していますが、添加物なので使いすぎると体に影響があるかもしれません。
うま味調味料を使うか使わないかは個人の自由です。
「絶対使ってはいけない」
「安全だから使っても平気」
「メーカーが言ってることは信じられない」
「食べ過ぎなければ問題ない」
いろんな意見があると思いますが、最終的に使うか使わないかを決めるのは自分。
うま味調味料の成分が昆布だしと同じとのことですが、それを理解した上で私はこれからもうま味調味料を「あえて使うことはない」と思います。
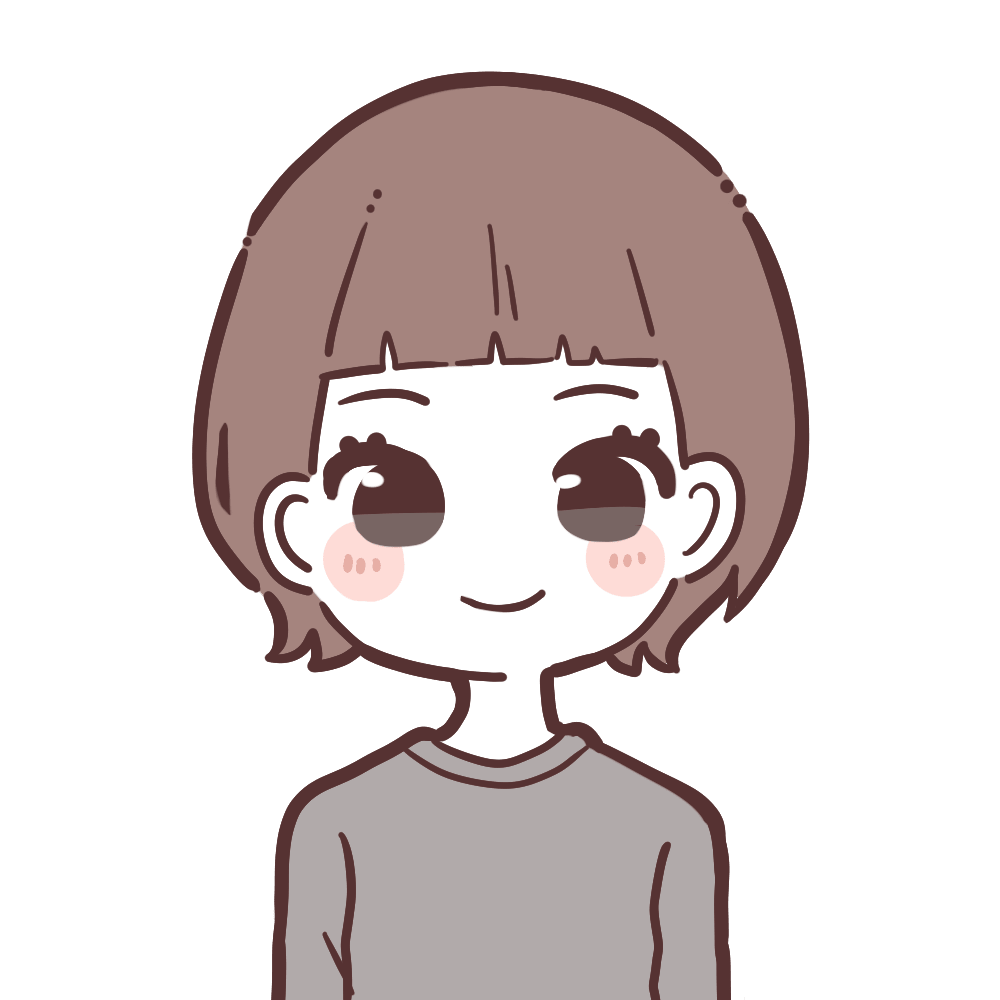
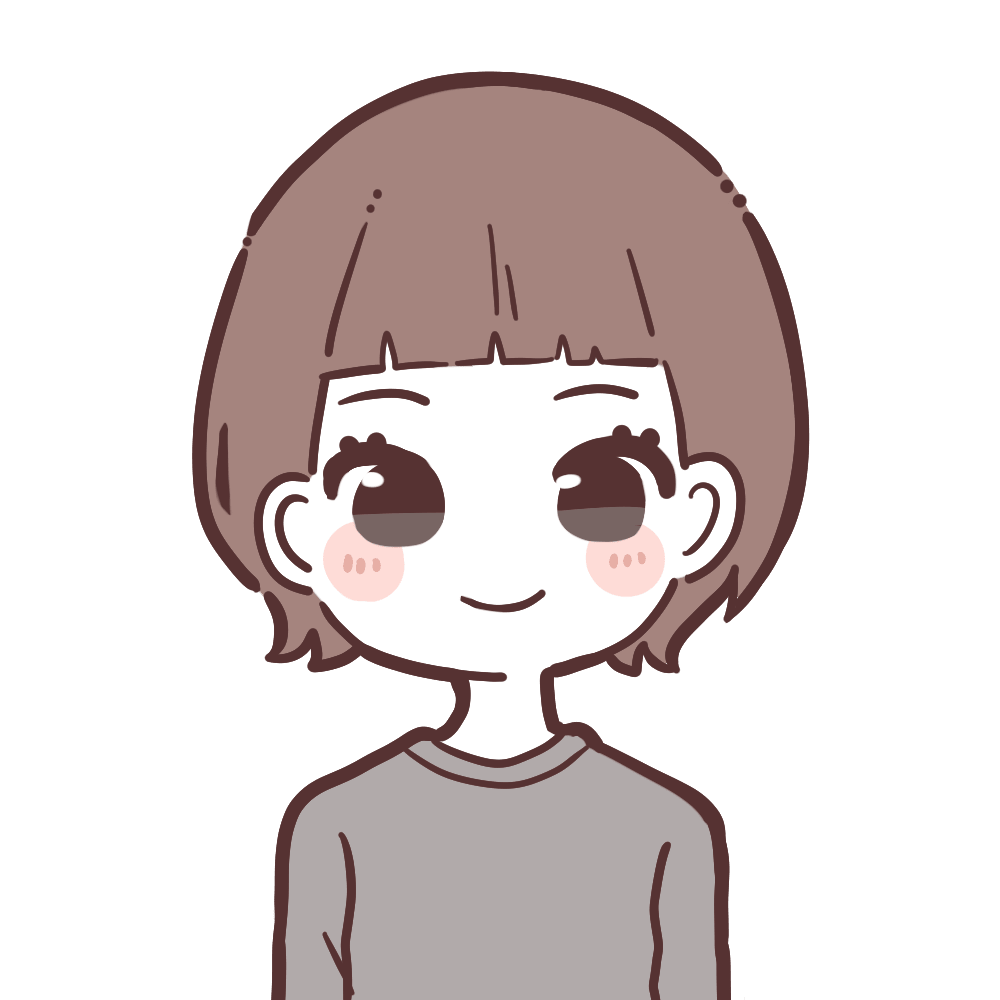
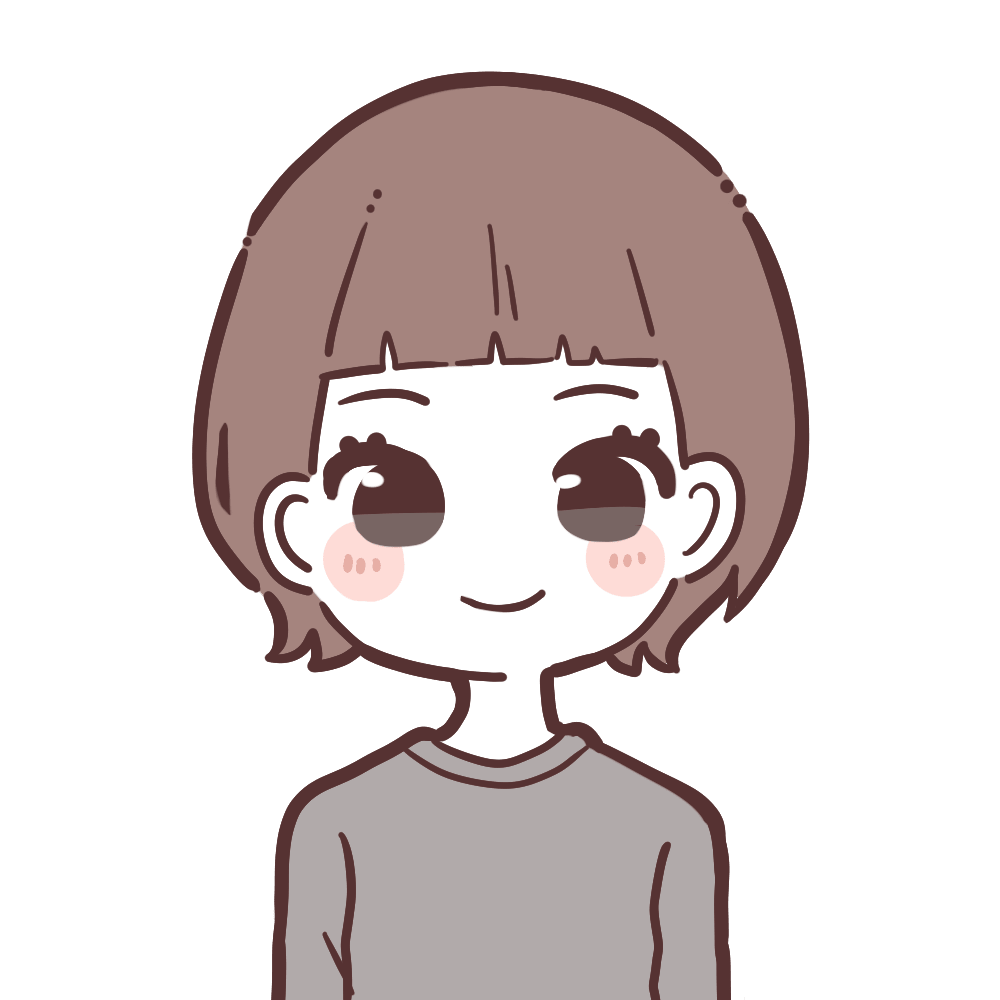
私には不要だと思うから
化学調味料は放送禁止用語?まとめ
- 化学調味料はNHKで「味の素」という名前が使えなくて作られた言葉だった
- 化学調味料からうま味調味料へ名前が変更されテレビでも使われることがなくなった
- うま味調味料の成分は昆布だしと同じグルタミン酸ナトリウム
- グルタミン酸ナトリウムは石油から作ることもできる
- グルタミン酸ナトリウムの安全性はWHOでも認められている
化学調味料という言葉がNHKの番組から生まれたということもビックリでしたが、化学調味料の定義がないことにもビックリしました。
化学調味料について深く考えたことがなかったですが、これも添加物に興味をもったから知ることができました。
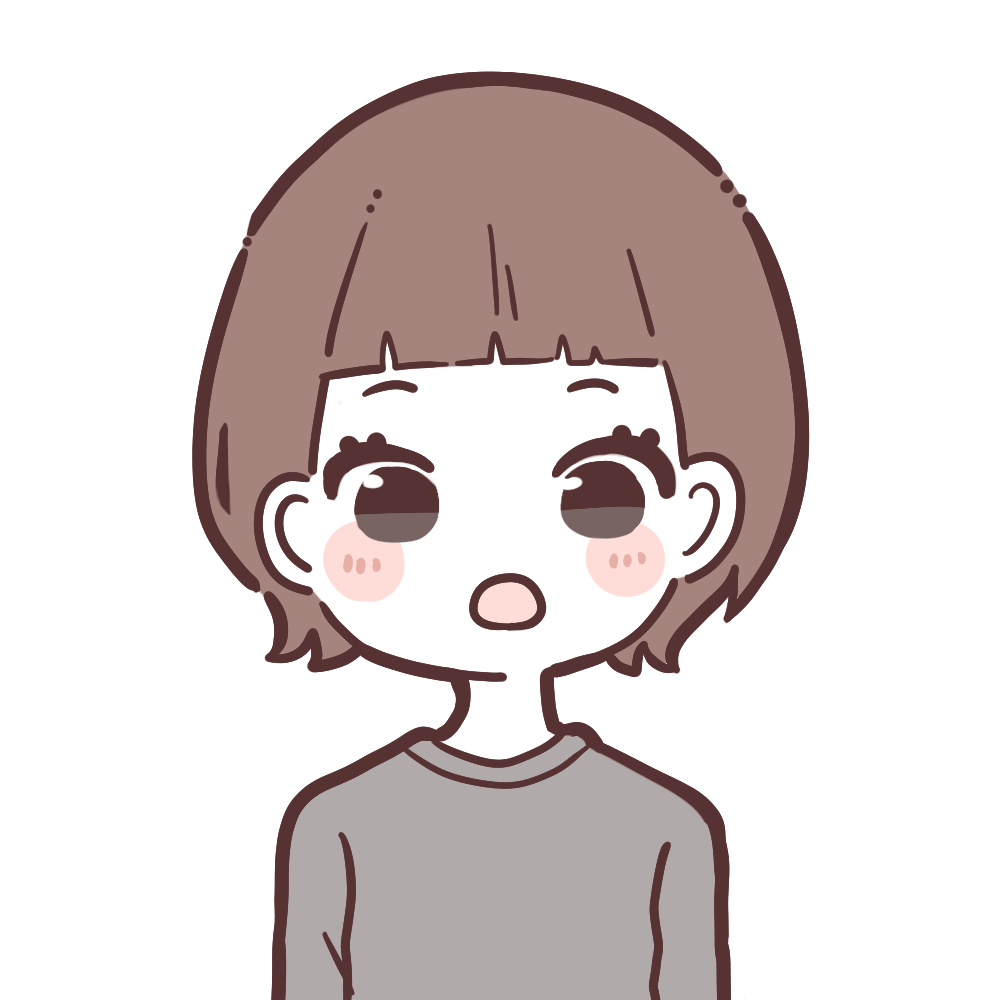
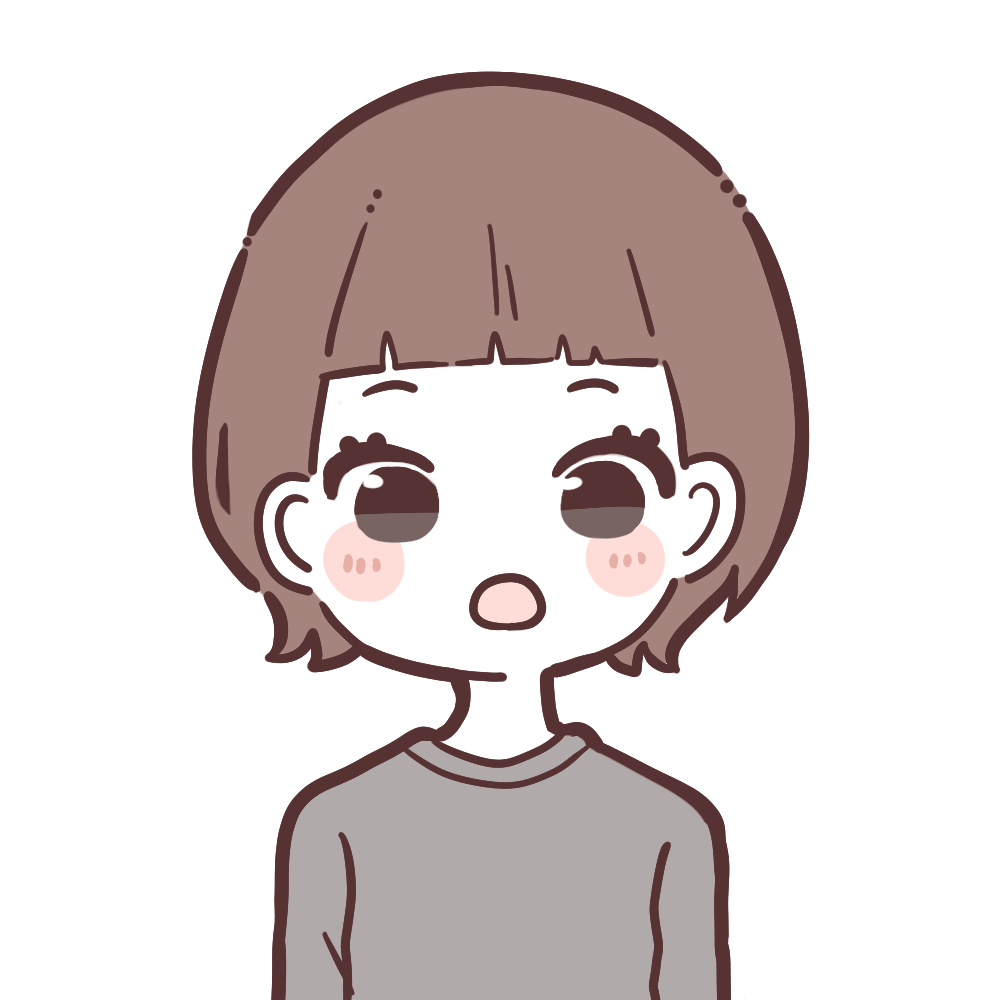
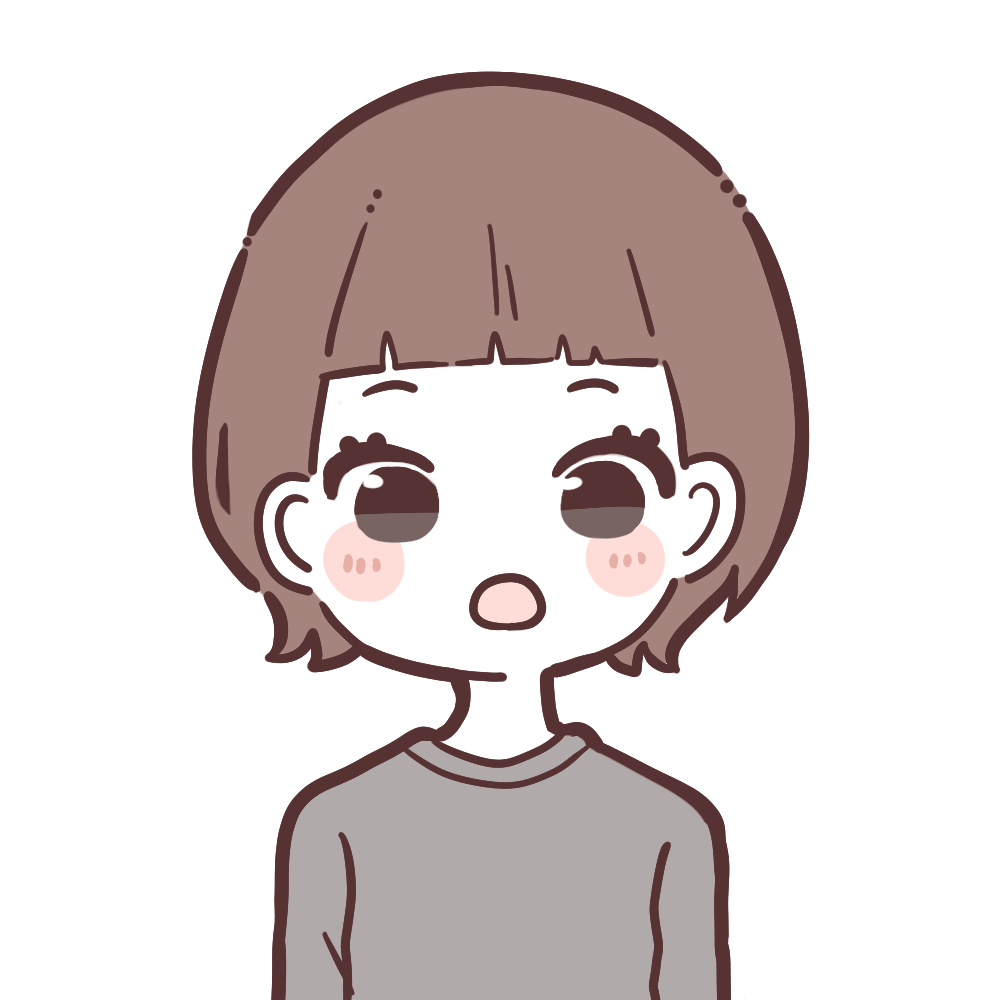
食品添加物の世界は奥が深い
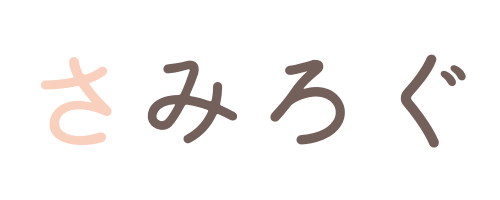

コメント